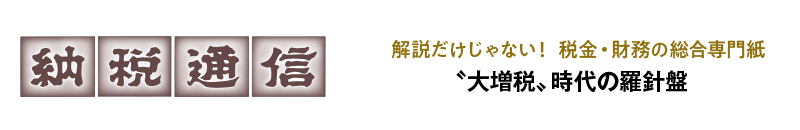

オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。専門記者による国税関連機関、税理士等への密着取材で培われた報道内容は、一般紙や経済・ビジネス雑誌では決して読むことはできません。
▼今週の注目記事 納税3845号1面より
後継者選びの遅れで生じる
事業承継リスク
「後継者が決定している中小事業者は全体の10.5%にとどまる」「廃業を予定している中小事業者は全体の57.4%」――。昨年3月に発表された日本政策金融公庫総合研究所(日本公庫総研)の「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)」は衝撃的な結果を伝えた。さらに17年版の「中小企業白書」では、後継者が決定している事業者の4割が後継ぎを選び始めてからその了承を得るまでに3年を超える期間を費やしていることが明らかとなっている。つまり、全体のわずか1割にしか過ぎない「後継者が決定している事業者」となるためには、3年超の説得・準備期間が必要だということだ。後継者選びには時間がかかる。これを先送りしてしまうことが、最終的には約6割の「廃業予定」につながっているといえるだろう。後継者選びが遅れることで生じる〝承継リスク〟について考えてみたい。
「後継者決定」1割、「廃業予定」6割の衝撃!
「決定」するまでに3年超
中小事業者の事業承継の第一関門は、なんといっても後継者を決定することにある。しかし、さまざまな理由から後継ぎ候補者がなかなか首を縦に振らず、了承してもらうまでに時間が掛かっている。自社株移転の負担軽減策などを講じ、後継者の早期決断を後押しする必要があるといえるだろう。さらに、ようやく後継者が決定した事業者であっても、その半数以上が「本格的な経営トップに育て上げるための育成期間は4年以上」かかっていると回答している。事業承継は長期戦になるものと覚悟したい。
日本公庫総研のアンケート調査によると、後継者が「決定」している中小事業者は全体の10.5%で、「未定」の20.0%、「時期尚早」の12.0%と合わせても4割程度に過ぎない。その一方で「廃業予定」は57.4%。今後、「未定」が結論を先送りして「未定」のままで後継者問題を放置していたとしたら、「廃業予定」の割合はますます増えていくことだろう。
後継者が決まっている中小事業者のうち、後継者選定を始めてから当事者の了承を得るまでにかかった期間が1年以内と答えた割合はわずか20・5%に過ぎず、1年超3年以内の42・4%を合わせても約6割だった。3年超5年以内は22・7%、5年超10年以内は10.5%、10年超も3.9%という結果で、約4割が了承を得るまでに3年超の時間がかかっている・・・(この先は紙面で…)
▼注目コンテンツ
 税理士新聞
税理士新聞

会計事務所の最新ビジネスニュースをはじめ、税理士業界・関連業界の最新動向をいち早く報道している専門紙です。税理士会の会報誌やビジネス雑誌では得られない、業界のウラ情報、ニッチニュースが厳選して掲載されています。
 社長のミカタ
社長のミカタ

『納税通信』の速報記事を詳細にダイジェスト! 『社長のミカタ』は、会計事務所とオーナー経営者を結ぶ月刊紙です。会計事務所のアーカイブとしてはもちろん、中小企業のオーナー社長必読の経営・税務情報が満載!!
 オーナーズライフ
オーナーズライフ

『オーナーズライフ』は、オーナー経営者の大きな関心事といわれる、事業承継対策と資産・相続税対策のニュースを縦軸に、謳歌すべき権利である円熟の上質生活の情報を横軸に、同族企業オーナーのビジネスと生活だけに焦点を絞った、まったく新しいフリーペーパースタイルの直送情報紙です。
Copyright © NP News Company. All rights reserved.
