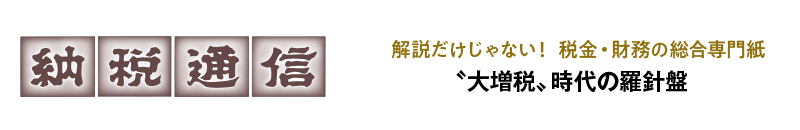

オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。専門記者による国税関連機関、税理士等への密着取材で培われた報道内容は、一般紙や経済・ビジネス雑誌では決して読むことはできません。
▼今週の注目記事 納税3866号1面より
功労者にどれだけ報いる?
役員退職金の〝相場〟
経営者などが退任時に受け取る「役員退職金」の税務は、数ある法人の申告手続きのなかでも納税者と課税当局の対立要因になりやすい。長年の貢献を数字にどう表せばよいのか、「不相当に高額」とはどれくらいを指すのかをめぐり、これまでに多くの事業者が国税と戦ってきた。役員の退職金は、どのように算出すればよいのか。
税法に明確な基準なし
ダイキン工業は、2024年6月に取締役会長を退いた井上礼之氏に対して、「特別功績金」として43億円を支払った。東京商工リサーチによれば、日本人の会社役員への退職金としては15年に退陣したオリックスの宮内義彦氏に対する退職金44億円に次ぐ金額だという。井上氏は約30年にわたってダイキンの経営をリードしてきた功労者であり、43億円の退職金も決して高額過ぎるものではない。
井上氏が受け取った金額まではいかなくても、誰だって退職金はなるべく多くもらいたいものだ。それが長年にわたり会社の舵取り役を務めてきた経営者であればなおさらで、オーナー企業の社長が自分の会社からどれだけ退職金をもらおうが、誰にも文句をいわれたくはない。
ところが現実はそうはいかず、中小企業の社長が受け取る役員退職金は、国税に否認されやすい項目のひとつとなっている。損金として認められる役員退職金に〝天井〟がないと、会社の利益をまるごと退職金に移すという利益処分が可能となってしまうからだ。
過去に役員退職金の損金算入が否認された判例を見ると、「隠れた利益処分に対処して課税の公平を確保」(94年名古屋地裁)や「利益処分である賞与に該当するものとしてこれを損金に算入しない」(81年岐阜地裁)など、過大な役員退職金は利益処分に当たるので認めないという見方がされてきたことが分かる。
役員退職金をめぐる税法上の規定は、法人税法34条と施行令70条に置かれている。しかしそこには、「業務に従事した期間、その退職の事情、同種の事業を営む規模の似た他法人の支給額などに照らし、退職給与として相当であると認められる金額を超える」部分についてが「過大」であるとしか書かれていない。具体的に何円までが妥当で、何円からが過大かは分からない。そのため経営者の貢献をどう評価するかという部分に解釈の余地が大きく、貢献度を最大限に評価したい企業と、高額過ぎる退職金を認めない国税側との間でもめる理由となっている・・・(この先は紙面で…)
▼注目コンテンツ
 税理士新聞
税理士新聞

 社長のミカタ
社長のミカタ

 オーナーズライフ
オーナーズライフ

